小児矯正とMFTにおけるマーケティング戦略
MFTは子を持つ母親の潜在的なニーズの1つ

昨今、小児の噛み合わせ改善療法の一環として「MFT:口腔筋機能療法」(Oral Myofunctional Therapy)が注目されている。
歯科医師向けコンテンツでもあるので、MFTの詳細は省くが「こどもの歯並び・噛み合わせ」などを含めた親の悩みや疑問は1つのマーケット(市場)と考えるのが正しい。
さながら、小児歯科と小児矯正を分別してしまうことは歯科医師として専門か否かという考え方にも偏りがちであるが、地域を顧客対象(患者対象)として小児歯科を行うのであれば少なからず経営的視点において考察はしなくてはならない。
子供の咬み方・話し方が気になる親
当社には40名ほどの歯科従事者兼内覧会スタッフが在籍しているのだが、そのほとんどが子を持つ親である。
当然に口腔内環境の管理・リテラシーは高いのであるが、一般社員・事務員などの子を持つ女性スタッフに話を聞いてみると、
「もちろん、自分の子供の咬み癖や歯並び、そういうことは気にしていますが、どこに聞けばよいか分からない」
という答えが返ってくる。
当然、当社のスタッフなのである程度、ネットで調べる能力はあるのだが、MFTという言葉や口腔筋機能療法というキーワードに日常で接触する人は少ないのではないかと思う。
小児矯正を増患したいのであれば
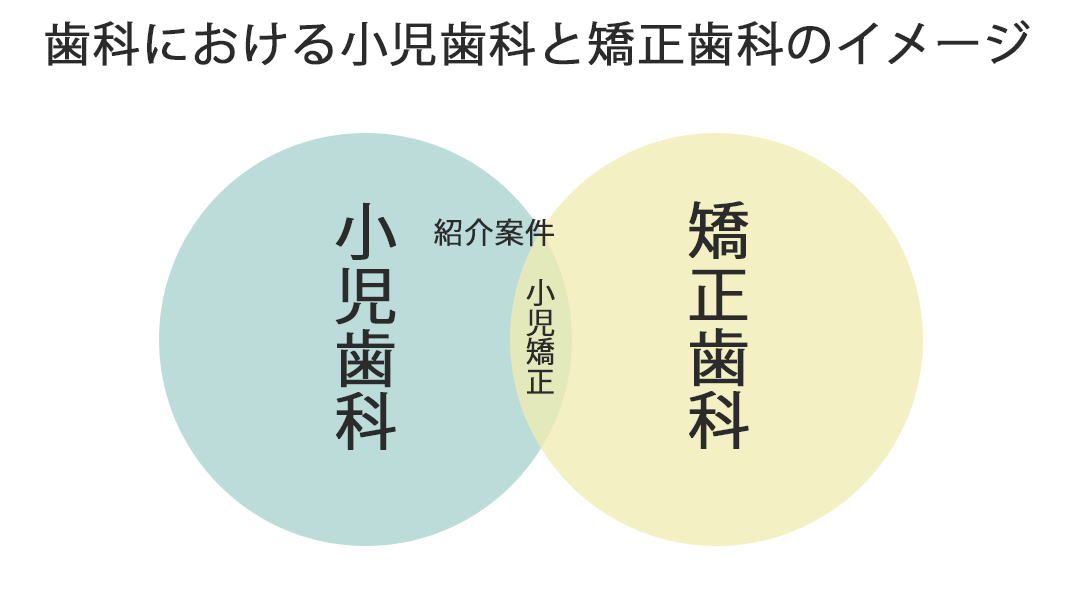
小児歯科と小児矯正を行っているのに別考えるのは非常に勿体ない。
企業の営業部で言う「取りこぼしの多い課」となる。むしろ営業マン単位であれば「数字の持っていないヤツ」である。
当然のことながら小児歯科と矯正歯科は別の科目であるが対象者は重なっている。
小児歯科と矯正歯科を分ける考えは必要だがユーザー側から見れば答えは1つの場所から欲しいと思うものであり、そこに直接的に「矯正相談会」で矯正歯科医に矯正相談だけを任せてしまうのは、ユーザー側に正しい情報をどれだけ提供できるかも疑問である。
歯科はすでに数の飽和で市場原理が介入し、サービス業化しているのは否めないし、勝ち組と負け組は明確である。
現実、私のクライアントに月間医業収益が5000万円を超える歯科もあれば、売れない八百屋程度の売り上げしかない診療所もある。(実際に売れていないように見える八百屋に限って2~3億売り上げていることが多い)。
つまり、小児歯科で拾い上げる矯正ニーズの間にMFTというソリューション(問題解決)としての手法を取り入れるという事は、広く小児矯正へのバトンタッチにもつながるし、小児のシェアを拡大させることが出来るコストもそれほどかからない増患対策になる訳である。
MFTで失敗する歯科医は小児で失敗している
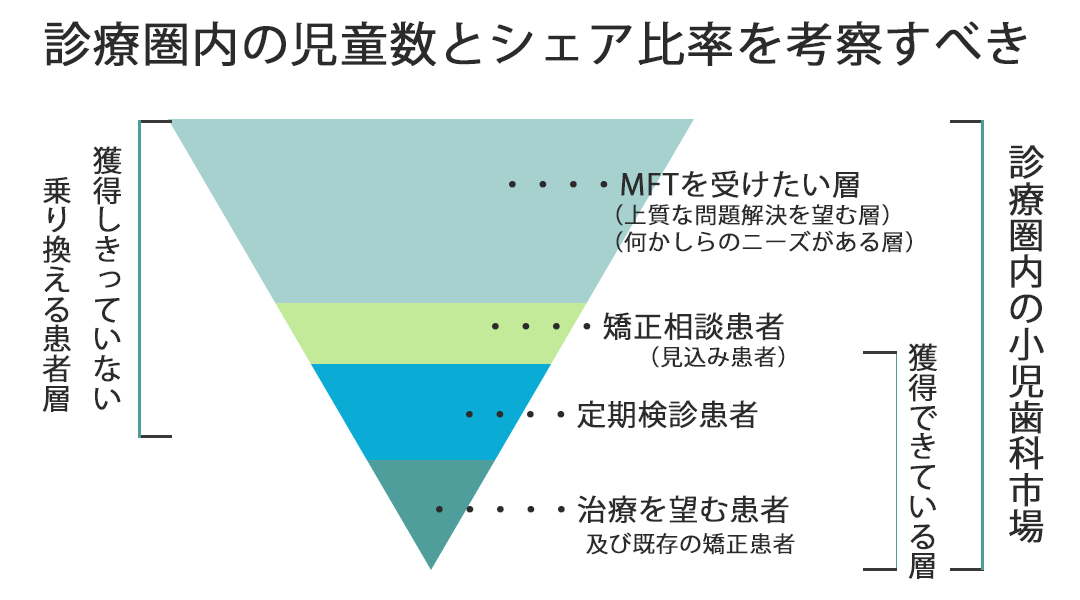
ただ、せっかくMFTという患者満足度の高い手法を取り入れても上手くいかないのは「情報発信」である。
歯科経営はすでにコンテンツ・マーケティングが全てと言っても過言ではない。
人気の記事
カテゴリー
タグ
ページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
定休日











